RevComm で音声処理を中心に研究開発を担当している加藤集平です。
私はADHD(注意欠陥・多動症)という障害を抱えています。ADHDを持つ人は日常生活でさまざまな困難に直面するもので、もちろん仕事をしていく上でも困難があります(障害を持たない人と同じやり方では困難に直面します)。私も例に漏れずさまざまな困難に直面していますが、2022年12月に本ブログで公開した記事では、当時それらの困難にどのように対処しようとしていたのかを紹介しました。また、弊社の働き方の特徴であるフルフレックス・フルリモート環境が及ぼす影響についても取り上げました。
本記事では、前回の記事の公開から2年半が経過し状況が変化したことを踏まえ、私が現在直面している困難とそれに対する対処、弊社の働き方の特徴であるフルフレックス・フルリモート環境が及ぼす影響について改めて整理してお伝えします。
内容に前回の記事と重複するものが多くありますが、この記事単体で読んでいただけるようにしたいと思ってのことです(ADHDの方は特に、複数の記事を行き来するのはつらいかと思います)。ご容赦くださいませ。
加藤集平(かとう しゅうへい)
シニアリサーチエンジニア。RevCommには2019年にジョインし、音声処理を中心とした研究開発を担当。ADHDと付き合いつつ業務に取り組む2児の父。
個人ウェブサイト X
→ 過去記事一覧
本記事を読むにあたっての注意
- 私はADHDを専門とする医師でもその他の専門家でもありません。ADHDに関する正確な情報は、専門家の発信をご参照ください 。
- ADHDの症状(困難に直面するポイントあるいは本人の特性)は人によって異なることが知られています。また、同じ症状に対して同じ対処が有効とは限りません。本記事で取り上げるのは私の症状と私が実践している対処法であり、万人に通用するものではありません。
- ADHDの診断は医師のみが行うことができます。自己判断はかえって困難を増大させるおそれがあります(例えば、症状が似た違う病気かもしれません)。他人を勝手にADHDだと断定することについても同様に、本人および周囲の困難を増大させるおそれがあります。
ADHDとは
ADHD(注意欠陥・多動症)とは、精神障害のうち発達障害に分類されるものの一つです。発達障害とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。発達障害の中でもADHDは不注意・多動性・衝動性の3症状を主な特徴としており、それらの症状の影響で日常生活・学業・仕事などに様々な困難が生じることがあります。かつては子供だけに見られる病気と考えられていましたが、現在では大人になっても症状が継続する場合があることが知られています。
私とADHD
私がADHDと診断されたのは、2017年(30歳頃)のことでした。当時は前年に発症した強迫性障害という病気の治療のために心療内科に通っており、通院・治療の過程でADHDであることが発覚しました。
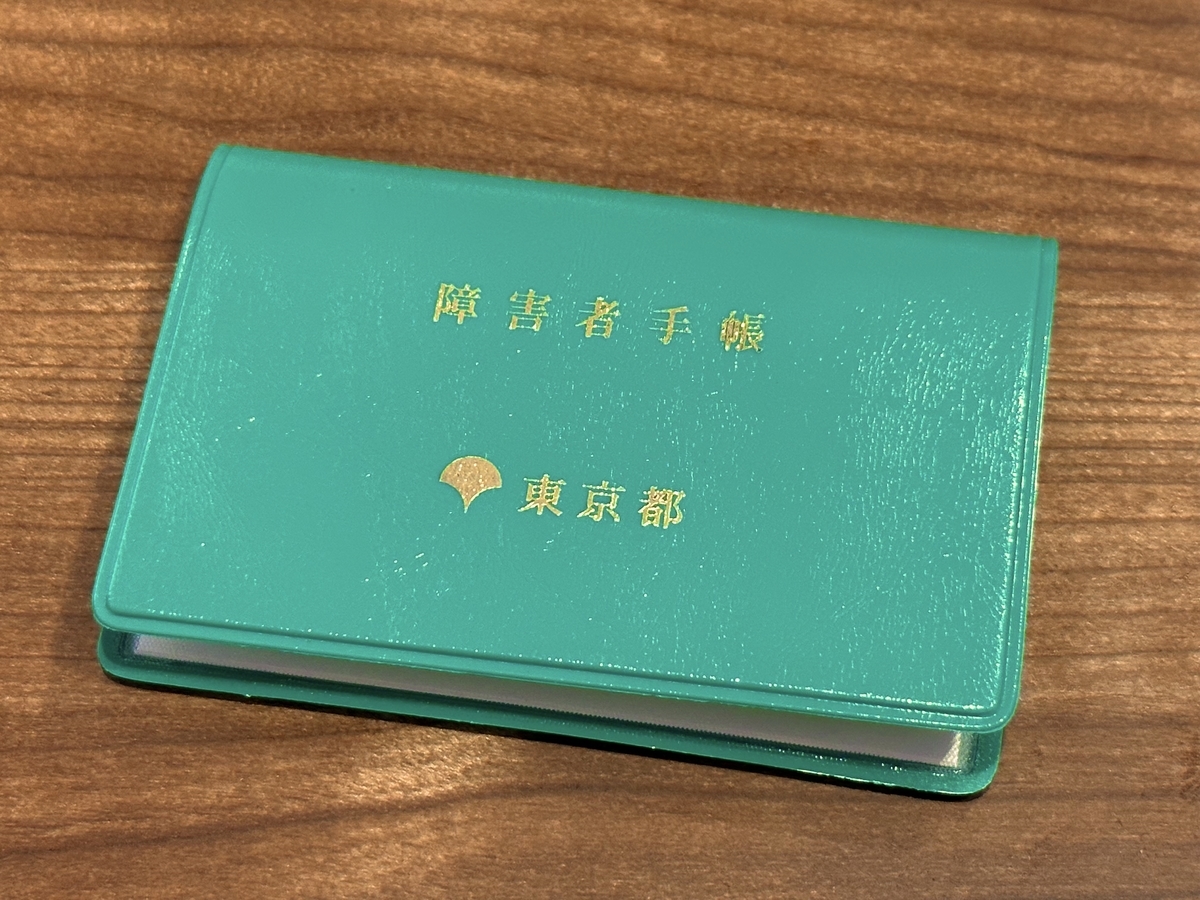
思えば物心ついた頃から忘れ物や物をなくすのは日常茶飯事で、部屋は常に散らかっており、コツコツ勉強することは決してなく、学校のテストではよく不注意で失点をしていました。
大人になり仕事を始めてからは、順序立てて仕事を処理することが苦手で締切に間に合わなかったり、他人に出した指示をすっかり忘れたり、単調な作業ですぐに寝てしまったり、体調に波があるために毎日8時間パフォーマンスを出し続けることが難しかったりして、仕事の遂行に支障をきたしていました。また、かつての勤務先では毎日オフィスに出社していたのですが、電話番をすることや周囲の話し声(雑音)が苦痛で頭がいっぱいになったりといった困難もありました。
診断を受けてからは、定期的に通院の上、服薬および日常生活の中での治療を続けています。この状況は2年半前と特に変わっていません。
フルフレックス・フルリモート環境における恩恵と困難
ADHDを持つ人にとって、弊社のようなフルフレックス・フルリモート環境は適しているのでしょうか?私の場合は恩恵のほうが大きく勝りますが、フルフレックス・フルリモートならではの、オフィス出社にはない困難も感じています。これらの恩恵と困難を紹介します。
恩恵
体調の波を吸収しやすい(フルフレックス)
ADHDを持つ人すべてに当てはまるわけではないと思いますが、私は体調に比較的大きな波があります。つまり調子のいい日と悪い日の仕事のパフォーマンスの差が大きくなるおそれがあります。現在は2年半前と比べてパフォーマンスの差は小さくなりましたが、依然として多少の波はあります。
フルフレックスの制度下では体調に合わせて比較的柔軟に勤務時間(長さおよび時間帯)の調整ができます。当然、打合せやプロジェクトの進行状況などの制約条件があるので完全に自由に調整できるわけではありませんが、それでも毎日絶対に決まった時間に仕事をしなければならない状況よりは安心感が違います。
静かな環境で仕事ができる(フルリモート)
自宅や家族構成などの諸条件に左右されますが、オフィスよりも静かな環境を用意することができる場合があります(私は用意できています)。私の場合は雑音が多い環境が苦手なので、静かな環境は集中力を高めるのに役立っています。
困難
自主的にやる気を管理する必要がある(フルフレックス・フルリモート)
フルリモート環境では、オフィスのように衆人環視の中で仕事をするわけではありません。人の目がない環境だとどうしても怠けやすくなります。しかし怠けすぎると、仕事の成果が出ず問題になります。
逆に、やる気に満ちあふれている時には過剰な長時間労働をするおそれもあります。フルフレックスの制度下では(法令の範囲内で)極端な時間の使い方をすることも不可能ではありませんが、健康の観点や、組織の一員として周囲と協調しつつ働く観点からは望ましくないでしょう。
ADHDを持つ人にはやる気のある時とない時の差が激しい人が少なくありませんが、やる気のない時に最低限のやる気を出すことと、やる気に満ちあふれている時に働きすぎないようにする工夫は、体調を整えつつ安定したパフォーマンスを出す上で重要だと考えています。
私の場合は、先述したように子育ての関係である程度決まった時間に働くことになっており、2年半前と比較して体調とパフォーマンスをより安定させることに繋がっていると感じています。
家事などの私生活と仕事のバランスを意識して取る必要がある(フルフレックス・フルリモート)
フルフレックス・フルリモート環境では、仕事中にいつでも私用を挟むことができます。特に在宅勤務の場合は、仕事の合間に家事をすることは珍しくないでしょう。
ところが、ADHDを持つ人には一度集中したら他のタスクになかなか移り難い傾向のある人が少なくありません(過集中)。つまり、家事を始めたらいつまでも仕事に戻れなかったり、逆に仕事に熱中して家事が疎かになったりすることがあります。
仕事に戻れないことは当然問題になりますし、家事が疎かになることも私生活においては問題になりえます。
フルフレックス・フルリモートとは関係のない一般的な困難
膨大なタスクを適切に管理する
前回の記事を公開した2年半前と異なり、現在の私は多数のプロジェクトに少しずつ関わるという働き方をしています。このような働き方においては、自ずとタスクの数は増え、しかもそれらを同時並行でこなす必要があります。ADHDを持つ人にとって、多くのタスクを同時並行でこなすことは一般に苦手なことの一つだと思います。私も苦手なので、対処する必要があります。
私が困難に対処している方法の例(★は前回の記事以降に新たに始めたこと)
「自主的にやる気を管理する必要がある」に対して
仕事前に着替える
在宅勤務では、打合せがなければパジャマのままでも仕事をすることが可能です。打合せがあっても、下半身はパジャマのままでもバレません。しかし、私の場合は気持ちを仕事に切り替えるために、仕事前に必ずパジャマから着替えることにしています。オフィスに出社していれば通勤時間で気持ちを切り替える人も多いかと思いますが、在宅勤務は通勤時間がないので代わりにしっかり着替えることにしています。パジャマよりも寝心地が悪いので、安易な昼寝を防止する効果も期待できます。

専用の仕事部屋で仕事をする
誰もが実践できる方法ではありませんが、私はほぼ仕事専用の部屋を用意しています。私生活の場と空間を分けることで、仕事に対するやる気を出しやすくなります。やる気に乏しい日でも、机に座ってしまえば仕事ができることは珍しくありません。特にADHDの人には、トリガーが大事であることは経験的にご理解いただけるかと思います。
★毎日ある程度決まった時間に働く
フルフレックスの精神に反すると感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分で決めた時間でいいので毎日ある程度時間を決めて働くことは、体調の安定に資すると実感しています。
私の場合は、2年半前と違って子供が保育園に通っている時間に大半の仕事を終える必要があり、自ずと毎日ある程度決まった時間に働くことになっています。自ら望んで決まった時間に働いているというよりは、そうせざるを得なかったので決まった時間に働いているだけなのですが、結果としてはいい方向に作用していると感じています。
★原則として規定の労働時間しか働かない
フルフレックスでも、1か月あたりの規定の労働時間や、それを超えた場合の残業という概念はあります。毎日ある程度決まった時間に働き、原則として1か月あたりの規定の労働時間の範囲内で働くことで、締切効果(締切直前だけ頑張れるアレです)が働きます。
私の場合は、子供が保育園に通っている時間に大半の仕事を終える必要があるため、自ずと労働時間に制限がかかります。この制限をうまく活かして、集中力を発揮することに成功しています。
★ポモドーロ・テクニックを活用する
ポモドーロ・テクニックとは、25分間の作業と5分間の休憩を繰り返すことで、集中力を維持して生産性を向上させるやり方です。定期的なリズムと短時間の集中が、やる気をうまく発揮し、かつ疲れすぎないことに繋がっていると感じています。
2年半前には既にリマインダーで過集中を防いでいましたが、対処がより洗練された方法になった感じです。
「家事などの私生活と仕事のバランスを意識して取る必要がある」に対して
私生活の時間はカレンダーをブロックしてしまう
前回の記事では、昼食を取り損ねるために昼食の時間 (12:00 – 13:00) のカレンダーをブロックしていました。
現在は昼食が自然と取れるようになったのでその時間はブロックしていませんが、起きてから子供を保育園に送るまでの時間と、迎えの後に子供が寝るまでの時間はブロックしています。こうすることで、その時間はしっかりと家事・育児に集中することができます。
「膨大なタスクを適切に管理する必要がある」に対して
★タスクをリマインダーで管理する
さまざまなベストプラクティスがあると思いますが、私が現在使っているのは広く知られたやり方の一つであるGetting Things Done (GTD) という方法です。単にタスクを列挙するだけでは特にADHDを持つ人にはつらいかと思いますが、GTDではタスクをシステマティックに管理することができます。タスクを管理する媒体は人それぞれですが、私はiPhoneのリマインダーを利用しています。
詳細は書籍や解説記事をご覧いただければと思いますが、個人的にはGTDを採用することで認知負荷が劇的に減り、目の前のタスクに安心して集中できるようになりました。これにより、より多くのタスクを、より少ない疲労で完了させることに成功しています。
2年半前はやっていたが、現在はやらなくなったこと
朝起きたら布団を畳む
仕事中に寝ることがほとんどなくなったので、やめました(行儀としては畳むべきかもしれません)。
コンテンツブロッカーを使う
コンテンツブロッカーを使わなくてもネットサーフィンをすることが減ったので、やめました。
適度に打合せを入れる
状況の変化により意識しなくても打合せが入るようになったので、わざわざ入れることはやめました。
労働時間をトラッキングする
タスク管理で十分に仕事が終わるようになったので、やめました。
スマートスピーカーに頼る(タイマー・アラーム)
2年半前は「洗濯をしたのに、つい仕事に熱中して何時間も干し忘れる」ことへの対策でタイマーを活用していましたが、自動で乾燥まで行ってくれる洗濯機に買い替えたので、やめました。
おわりに
2年半前とは生活も業務内容も随分と変わり、それに伴って困難や対処も変わりました。全体としては、日々工夫を重ねることで、より上手に対処できるようになったと感じています。
なお、以上の困難や工夫は私にとって一部であり、他にも仕事・私生活を問わず様々な困難に対してさまざまな工夫を日々行っています。また、周囲の方々の支援なくして良好な社会生活を送ることはできません。改めて家族やRevCommの仲間をはじめとする周囲の方々に感謝いたします。